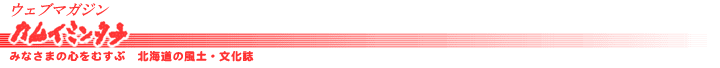ウェブマガジン カムイミンタラ
 2009年01月号/ウェブマガジン第25号 (通巻145号) [特集]
2009年01月号/ウェブマガジン第25号 (通巻145号) [特集]
従来の学問分野をこえた研究拠点
北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター
北大に誕生した人獣共通感染症リサーチセンターは、インフルエンザ(流行性感冒)ウイルスなど人間と動物がともに感染し、人間社会に脅威をもたらす病原体を研究する世界初の拠点。地道な調査や実験を積み重ね、感染症の予防や治療に大きな貢献が期待されています。
野鳥とニワトリの防疫対策

北大人獣共通感染症リサーチセンター
2008年春、道東の別海町と佐呂間町でオオハクチョウの死がいが発見され、検査の結果、病原性の高い鳥インフルエンザウイルスが検出されました。北海道庁はただちに半径30キロ以内にある養鶏場に消毒を命令、周辺の監視体制を敷きました。それと同時に、このウイルスは高病原性であっても、それは鳥に対してであり、人間にはほとんど感染しないことを周知させ、道民に冷静な対応を呼びかけました。
4年前の2004年の1月から3月にかけて、山口県、大分県、京都府と連続してニワトリなどが高病原性の鳥インフルエンザウイルスに感染するという事態が生じました。その対策としてとられたのが、発生農場の鳥類を丸ごと処分するという方法。おびただしいニワトリが地中に埋められる衝撃的なシーンがテレビで放映されました。

インフルエンザウイルス(人獣共通感染症リサーチセンター提供)
山口県の養鶏場ではニワトリ3万5千羽、大分県ではペットのチャボとアヒル、そして京都府ではじつに22万5千羽という数のニワトリが殺され、埋められました。そこで素朴な疑問も持ち上がります。ワクチンなど治療薬は使えなかったのか?本当にここまでしなければならないのか?
飼育されている鳥すなわち家禽(かきん)や家畜に対する厳格な対応、そして野鳥の感染死に対する冷静な対応、これらは、ある学者による長年の研究を元に確立された対策法でした。その学者が北海道大学大学院獣医学研究科(獣医学部)微生物学教室の教授で人獣共通感染症リサーチセンターのセンター長でもある喜田宏(きだひろし=65)さんなのです。喜田さんは言います。

喜田さん
「ニワトリのインフルエンザでは、中国、ベトナム、インドネシア、エジプトでワクチンによる対策をとっています。しかしワクチンは個体の症状は抑えても、ウイルスの排泄は続くので、見えない流行が広がってしまう。終わりのない感染の連鎖にはまってしまうのです。日本ではワクチンを使用せず、発生した農場の鳥を処分することで感染の拡大を抑えています。国際獣疫事務局(OIE)もこの成果に注目し、ワクチンを使わない動きが広まっています」
感染したニワトリだけでなく、同じ場所にいる鳥を丸ごと隔離処分したのは鳥インフルエンザウイルスが、ほかの場所まで広がらないための対策でした。そして鳥インフルエンザより、毎年冬になると猛威をふるう従来からある人間のインフルエンザの方がよっぽど危険だと喜田さんは言うのです。
「高病原性鳥インフルエンザは62カ国に広まっているが、これまで死んだのは245人しかいません。人間の中でも鳥インフルエンザに感受性の強い人が死んでいるんです。その一方で毎年流行するシーズナル(季節性)のインフルエンザでは、日本だけで何千人もが死んでいます。どっちのウイルスが怖いのかは明らかです」
学士院賞を受けた研究
喜田さんは札幌南高校から北大獣医学部に進み、大学院修士課程を修了後、武田薬品工業に入社、7年間ワクチンなどの研究に携わったあと、1976年から北大で研究者の道を歩みました。
「(製薬会社の研究室で)香港インフルエンザウイルスを扱ったスタッフが、ワクチンを打っていたにもかかわらず、次々に40度の熱を出してしまった。そのころは抗原変異の積み重ねで大きな変異が起きるというのが一般の理解でした。でも納得できない。新型ウイルスはただの抗原変異ではない。それで勉強して出直すため大学に戻りました」

カモのフンをひたすら拾う(モンゴルで=人獣センター提供)
従来のワクチンでは効かない新型インフルエンザウイルスの出現に、人間だけでなく動物が関与する可能性のあることを、アメリカやオーストラリアの研究者が示唆する論文を発表していました。獣医学部出身で、しかも製薬会社でインフルエンザワクチンを開発していた喜田さんにとって、人間と動物が関わり合うウイルスの研究はまさしく天命だったのかもしれません。
北大に戻ってさっそく研究生活を始めますが、それは哺乳動物と鳥類の疫学調査に明け暮れる日々でした。船に乗り込んで海鳥を調べたり、アラスカやシベリヤに飛んでひたすら野鳥のフンを拾っては持ち帰り、ウイルスを探すというフィールドワークと実験の地道な繰り返しです。まさに雲をつかむような状態から、1つまた1つと知見を積み重ねていったのです。

研究室では地道な実験が
それから約30年が過ぎた2005年、喜田さんは日本の学術賞では最も権威があるとされる日本学士院賞を受賞しました。それを伝える北大の「全学ニュース」には次のようなことが功績として挙げられています。(文は簡略化しています)
〔人間と動物のインフルエンザAウイルス遺伝子の起源が野生の水鳥、とくに渡りガモの腸内ウイルスにあることを突き止め、カモが鳥類やヒトを含む哺乳動物のインフルエンザAウイルス遺伝子の供給源であり、自然宿主(しゅくしゅ)であることを明らかにした〕
〔ブタは哺乳動物のウイルスだけでなくカモのウイルスにも同時に感染することがあり、そのとき両ウイルスの遺伝子によって新たなウイルスが生まれ、1968年のA香港新型インフルエンザウイルスが渡りガモ→アヒル→ブタ→ヒトの経路で出現したことを明らかにした〕
〔アラスカ、シベリアおよび中国でインフルエンザウイルスの調査を行い、カモの営巣湖沼がウイルスの貯蔵庫になっていることを突き止め、新型ウイルスが登場する中国南部にはカモによって運ばれることを明らかにした〕
144通りをライブラリーに
インフルエンザウイルスはカモのお腹の中で増え、北方の湖でフンから水に溶け出したウイルスは、冬は冷凍保存されます。北方の湖沼で夏を過ごしたカモは秋になるとウイルスをお腹に入れたまま南方に渡ってきて、人間社会に近づきます。そしてフンによってウイルスがまき散らされ、家禽を通してブタが感染し、同時に人間の流行ウイルスに感染すると、新たな形のウイルスが誕生する、ということです。人間または実験動物しか扱わない従来の医学ではとうてい到達することのできない新たな発見でした。
A型、B型、C型とあるインフルエンザのウイルスでとくに危険なのが、さまざまな形のものが現れて、それまでのワクチンが効かなくなるA型です。ウイルスの表面にHAとNAというたくさんの突起があり、それらが変異し、これまでHAでは16種、NAでは9種の変異体が発見されています。インフルエンザAウイルスはそれらの組み合わせでH1N1、H1N2などの略称で表現され、理論上は16×9=144種類の亜型があることになります。そしてH1N1のワクチンはH2N2のウイルスには効かないという現象が起こるのです。
これまでパンデミック(世界的大流行)インフルエンザと呼ばれるもののうちスペイン風邪(1918年~)はH1N1、アジア風邪(1957年~)はH2N2、香港風邪(1968年~)はH3N2、ソ連風邪(1977年~)はスペイン風邪と同じH1N1でした。

セミナー「パンデミックインフルエンザにどう備えるか?」
喜田さんとそのスタッフたちは、アラスカやシベリアなどに出かけてはひたすらカモのフンを集め、144種になるはずのウイルスを蓄積していきました。しかしどうしても自然界で発見できなかったものもあります。それらは実験室で人工的に作り出し、144種すべてをそろえました。こうしたウイルスはマイナス80度の冷凍庫に保管されて「ライブラリー」と呼ばれ、必要なときにはいつでも利用することができます。
2008年12月には札幌のホテルでグローバルCOEセミナー「パンデミックインフルエンザにどう備えるか?」と題する公開講座が開かれました。グローバル(世界的)COEのCOEとはセンター オブ エクセレンス(center of excellence)で「卓越した研究拠点」。世界トップレベルの研究を重点的に支援し、その研究・教育拠点をつくっていこうという政府の政策で、その中に北大の「人獣共通感染症制圧のための研究開発」が入っています。

ウエブスターさん
講演したのはアメリカのロバート・G・ウエブスター博士と喜田さん。ウエブスターさんは1950年代から一貫して、動物インフルエンザと人間のインフルエンザとの関連について研究してきた世界的権威です。世界的学者2人の講演とあって、会場はイスを追加して満員になるほどの盛況、ウエブスターさんがパンデミックインフルエンザの歴史と今後の見通し、喜田さんがこれまでの鳥インフルエンザ研究の概略と季節性インフルエンザ対策の重要性を、ともに英語で語りました。
続くBSE、サーズ…
「鳥インフルエンザ」という言葉が一般の人に広く知れわたったのはいつごろでしょうか。1997年に香港では新型のインフルエンザ(H5N1)によってニワトリが大量死し、人間も6人が死亡するという事態が発生、日本国民にも衝撃を与えました。ただしこのときはマスコミでも鳥インフルエンザという言葉はあまり使っておらず、主に新型インフルエンザという言い回しでした。
ちなみに北海道新聞のデータベースで「鳥インフルエンザ」を検索すると、97年は記事1本のみで、その後2002年まで1本または0本でした。ところが2003年になると6本が現れ、2004年には突如671 本にも跳ね上がりました。
当時は世界中で新たな感染症が取りざたされた時期でした。2001年には日本でもBSE(牛海綿状脳症)問題が発生、2002年には中国でサーズ(SARS=重症急性呼吸器症候群)が発生しました。狂牛病やサーズといった不気味な呼び名もあって、日本国民に言い知れない恐怖感を植え付けました。
2003年に香港でふたたび鳥インフルエンザによって1人が死亡、翌04年に日本の養鶏場でも感染が確認され、大量処分という対策がとられました。鳥インフルエンザという文字が毎日のように新聞紙上をにぎわせたのです。

フリーザー室や実験室はモニターで一元管理されている
喜田さんたちは、その間も地道な研究を続けていました。北大全学ニュースの喜田さんの功績には次のようなことも挙げられています。
〔1997年に香港でニワトリからヒトに感染した強毒のインフルエンザがシベリアから飛来したカモのウイルスによるものであることを明らかにし、そのワクチンを試作、効果を実証した〕
ニワトリだけの感染なら隔離処分する方法で済みますが、人間が感染するとなると話は別。予防のための先回りとしてワクチンの研究が必要なのです。
そんな世界情勢の中で、2005年に人獣共通感染症リサーチセンターは世界初の研究拠点として新設されました。このセンターのミッション(使命)はつぎのように明記されています。
〔人獣共通感染症は、自然界に由来する微生物を病原とするので、当面、根絶は不可能である。その発生を予測し、流行を防止する「先回り戦略」によって克服すべき感染症である。すなわち、人獣共通感染症の原因微生物の起源と自然界における存続のメカニズム、侵入経路および感染、発症と流行に関与する諸要因を明らかにして、はじめて先回り対策をたてることができる。人獣共通感染症の克服に向けた研究・開発、予防・診断・治療法の開発と実用化、情報と技術の社会普及、人獣共通感染症対策専門家の養成は喫緊の国家・国際課題である。北海道大学人獣共通感染症リサーチセンターは、これを具現するための中核拠点として、「人獣共通感染症の克服」に向け、一貫した研究教育活動を行う〕
要するに研究領域を自然界に広げることで感染症の仕組みを究明し、その対策を講じること、そして研究成果を広く知らしめるとともに人材を育成していく、ということでしょう。これは喜田さんが長年のインフルエンザウイルス研究で積み重ねてきたきたことそのものです。
その方法があらゆる人獣共通感染症に通用します。方法論が確立しているからこそ、このセンターの開設が可能だったとも言えるのでしょう。ただしセンターの新設といっても、当初は獣医学部や工学部に間借りしており、2007年9月に新たな建物が完成し、名実ともに拠点ができあがりました。
異分野の専門家が集結

研究室の高田さん(左)とスタッフ
北海道大学北側の農場にいま大学関連のビルが次々に建設され、それらの建物群の一帯は北キャンパスと呼ばれています。その一画に2階建ての北海道大学人獣共通感染症リサーチセンターがあります。
1階にはインフルエンザウイルスなどの病原体を扱う実験室や、ウイルスなどを保存するフリーザー室、電子顕微鏡室など日本最先端の設備、2階には研究員室などが配置されています。教員スタッフは喜田センター長を含めて12人。いずれも博士の学位を持っていますが、獣医学、医学、農学、工学とさまざまで、出身分野がそれぞれ違っていることが分かります。

ウイルスの研究に欠かせない電子顕微鏡
副センター長でもある高田礼人(あやと)さん(40)は獣医学部微生物教室で学んだ喜田さんの教え子です。これまでアラスカやシベリアに行ってはカモのフンを拾い集めてきましたが、今もそれは同じで、最近はモンゴルに行くことが多くなりました。
「もともとは自然界にはどんなウイルスがいるのか、ということで集めたのですが、今は監視という要素が強くなっています」
センターでは単にインフルエンザウイルスを集めるだけでなく、その変異を予測できないかという試みも始まっています。ウイルスの遺伝子についての過去の膨大なデータを集め、コンピューターを使ってその変異を予測するのです。実現すれば、その型のワクチンをあらかじめ用意し、来たるべき流行に備えることができます。まさに先回りです。またインフルエンザに感染した人間を治療する新たな薬の開発にも着手しています。

P3動物実験室
結核も研究対象です。かつての日本で猛威をふるい、予防接種や抗生物質の投与によって根絶したかに見られたこの病気が近年また復活し「結核は過去の病気ではない」と叫ばれるようになりました。集団感染したり、治療薬の効かない新たな菌が次々に現れ、日本では毎年2千人以上が死んでいるのです。結核は猿や牛などにも感染する人獣共通感染症です。センターでは結核にかかっているかどうか、またどういう治療薬が有効かといったことが簡単に診断できる方法などを研究しています。
ザンビアでエボラ出血熱を

ザンビア大学獣医学部は北大の全面協力で発足した
(以下 人獣センター提供)
2007年5月、北大人獣共通感染症リサーチセンターはアフリカのザンビア大学内に共同研究拠点を設けました。
1984年に日本の無償援助でザンビア大学に獣医学部が新設されましたが、そのとき全面協力したのが北大獣医学部でした。そして教員たちがジャイカ(JICA=国際協力機構)の専門家として次々に派遣されて指導し、その後ザンビアから北大に留学生が来て学位をとるといった交流が続いていました。そんな関係から『感染症の宝庫』とまでいわれるアフリカに拠点を設けたのです。
副センター長の高田さんたちは、そこを拠点にアフリカで発生し感染したときの致死率が非常に高いエボラ出血熱の研究を始めています。高田さんは世界でも数少ないエボラ出血熱の研究者で、アメリカ留学時から取り組みました。自然宿主や感染経路についてはまったく分かっていませんが、コウモリが関係しているらしく、高田さんたちはザンビア政府から許可をとってコウモリを捕獲、採血調査をしています。

エボラ出血熱の研究(コウモリの調査)
まさに喜田さんがインフルエンザ研究でたどってきた道とそっくりな道に踏み出したのです。ただエボラ出血熱は感染症の中で最も危険度の高い1類に分類され、それを扱うにはレベルのもっとも高いP4と呼ばれる実験室が必要です。ところが人獣共通感染症リサーチセンターの実験室はそれよりレベルの低いP3とP2で、日本国内にはP4の施設はあるものの近隣住民の反発などから利用できず、高田さんはカナダに行って実験しています。
共通感染症研究はエコロジー研究

共通感染症研究はエコロジー研究
「高田くんには(エボラ出血熱の)自然宿主を明らかにしなさいと言っている。自然宿主が明らかになって、伝播(でんぱ)経路が明らかにならない限り、手をこまねいて見ているしかありません。人獣共通感染症をコントロールするには自然界を相手にしたエコロジーの研究こそが大事です。実験室にこもっているだけでは感染症は理解できません」と喜田さんは言います。
インフルエンザやエボラ出血熱などの人獣共通感染症は近年発生頻度が高くなっています。かつては自然界の動物たちの間で静かに受け継がれていたウイルスなどが、自然環境の変化や人間と野生動物との接近によって、人間社会にも入り込んでいるのです。それらがどこで生まれ、どういう経路をたどっているかの研究を行い、集められたウイルスなどをライブラリー化し、どんな病原体として人間社会に現れるかといった先回りの研究が必要です。それは人間を生態系を構成する一員としてとらえ、自然環境や物質循環、社会状況などとの相互関係を考えていく科学、すなわちエコロジーなのです。
北大の獣医学部は「動物のお医者さん」という漫画やテレビドラマによって人気に火がつき、入学試験の難易度は医科大学なみです。しかし人気の要因が「動物のお医者さん」だけだとしたらブームで終わっていたはずですが、その人気はまったく衰えていません。喜田さんのような地道で独創的な研究が行われ、多くの優れた研究者を輩出していることが認知されたためなのでしょう。
「WHO(世界保健機関)やOIE(国際獣疫事務局)といった国際機関に意見を言えるようなエキスパートを育てたい。そういう研究所にしていきたいんです。そのためにも、みんなしっかりした研究をして欲しい」
北大の人獣共通感染症リサーチセンターは自らが研究・教育するだけでなく、帯広畜産大学、東北大学など6つの大学と「人獣共通感染症研究クラスター」を形成、その中心を担っています。喜田さんを土台に、多くの研究者たちによる多くの研究成果がこれから積み上げられようとしています。
2009年には「感染列島」という映画が公開されるなど、日本では感染症についての関心が高まり、危機感も強くなっています。しかしいたずらに危機感を煽るのではなく、研究に基づいた確かな理論で、危険を伝え、ときには冷静な対応を求めることも必要です。こうしたことを可能にする北大人獣共通感染症リサーチセンターへの期待は高まるばかりです。